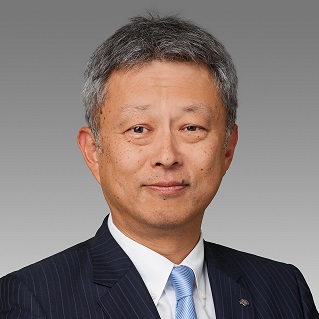
野村資本市場研究所は、金融資本市場の中長期的・構造的なテーマを専門的に調査・研究する機関として2004年に発足し、以後、20年を超える活動を継続してきました。また、野村サステナビリティ研究センターは、2019年12月に野村資本市場研究所内に設立され、5年以上にわたり、サステナビリティに関する研究活動を行ってきました。野村資本市場研究所及び野村サステナビリティ研究センターがそれぞれ設立から20年、5年という節目を迎えるにあたり、これまで支えてくださった皆様へ感謝の気持ちをお伝えするべく、金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現するという思いを込めて、各研究員が論文を執筆しました。
2025年を生きる私たちは、時代の大きな転換期に直面していると言えるでしょう。不確実性が高まる世界経済、生成AIによる産業構造の変化、人口減少・少子高齢化、さらには気候変動が地球環境に及ぼす影響、などの問題が山積しています。その中で、進むべき方向性を予見することは決して容易ではなく、過去と現在を丹念に調査・分析し、未来を見通すことの重要性がこれまで以上に高まっています。野村資本市場研究所では、この進取の精神のもと、長年にわたり政策提言や資本市場へのオピニオンを発信してきました。この度、設立20周年、5周年を機に執筆した論文では、資本市場をめぐる長期的かつ構造的なテーマについて、時代の変遷を調査・分析し、今後の展望を示しています。
当研究所の論文が、金融資本市場関係者を含む多くの方々にとって、新しい時代に向けての発想や行動の糧となることを心より期待しています。野村資本市場研究所は、この先の未来も、金融資本市場の健全な発展に貢献し、皆様のパートナーとして共に歩んでまいる所存です。
最後に、お世話になっておりますすべての関係者の皆様に、改めて、厚く御礼申し上げます。
2025年10月
野村資本市場研究所
取締役社長
稲井田 洋右
林 宏美、西山 賢吾
要約
- グローバルな取引所間の競争と再編が起こる過程で、先進国を中心とした証券取引所では、新規公開、増資といった発行市場における「資金調達」の役割が低下し、株式の売買などの流通市場における「取引」の役割がより重視されるようになった。一方で有形無形のコスト負担増等に伴う世界的な上場企業数の減少が見られる中、存在感と競争力を高めるための取り組みが各国の取引所で行われている。
- 米国では、ニューヨーク証券取引所(NYSE)、Nasdaq、Cboeという三大証券取引所グループに属さない、第三極の証券取引所を設立する動きが複数見られる。投資家のニーズに応えることを追求する会員制組織のメンバーズ取引所(MEMX)、長期志向の企業と長期志向の投資家を結ぶ場を提供するロングターム証券取引所(LTSE)、高頻度取引(HFT)の影響を少なくする工夫をし、公正な取引所を目指すインベスターズ取引所(IEX)等がある。
- 日本では、東京証券取引所による「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願いについて」の公表や市場区分の見直しなどにより、グローバルな取引所間競争に打ち勝つとともに、日本企業の競争力も高めるという「ウインウイン」の達成に向けた、上場企業の「質」向上に対する働きかけの積極化が注目される。
- その一方で「ウインウイン」を達成するためには、独自の取り組みを進めている米国、さらにはここまで日本での取り組みにおいて参考としていた英国等、他国の動向にこれまで以上に注意を払いつつ、歩みを進めていく必要があるだろう。
西山 賢吾
要約
- 日本における過去20年のコーポレートガバナンス議論のテーマは、「会社はだれのもの」論が盛んであった2005~2008年頃、コンプライアンスが強く意識された2009~2012年頃、成長戦略の中の重要施策とされた2013~2018年頃、そしてサステナビリティ(持続可能性)への関心が広がった2019年~現在と変遷してきた。
- 第二次安倍政権下で成長戦略の柱としてコーポレートガバナンス改革を取り上げてから10年が経過した。この間、一定の成果は見られるものの、国際的に見たROE(自己資本利益率)は依然として低いことや、企業の保有現預金の積み上がりなどの課題が残る。企業の収益性や資本効率性を高め、経済システムに良い「お金の流れ」を作るというコーポレートガバナンス改革の目的達成に向け、さらに歩みを進めることが期待される。
- コーポレートガバナンス改革が進んだことで、株式保有を巡る2つの変化が生じた。一つは、株式保有構造が取引関係の維持、発展を主な保有動機とした政策保有主体から、インカムゲインやキャピタルゲインの獲得を主な保有動機とする純投資家主体へ変化したことである。
- もう一つは、保有先企業の経営に関心を持ち、経営陣による企業価値向上への健全なリスクテイクを後押しすることが株主・投資家の重要な役割と期待されるようになったことである。これらの変化により、改革を一段と進める上では、企業と株主・投資家間で「緊張感を孕んだ相互信頼関係」を基礎とした新しい関係の構築が不可欠といえるであろう。
関 志雄
要約
- 習近平総書記が提唱する「新質生産力」とは、従来の経済成長モデルから脱却し、革新(イノベーション)が主導的役割を果たし、高度な技術、高効率、高品質という特徴を備えた先進的な生産力の形態を指す。中国において、新質生産力を向上させることは、持続可能な発展を実現し、厳しさを増す内外環境の変化に対応するための重要な手段として位置付けられている。
- 新質生産力を高める原動力は、科学技術革新、産業の高度化、生産要素の質と配置の改善と、三者の相乗作用である。中国は、科学技術革新を加速すべく、挙国体制の下で、科学技術の自立自強を目指しており、特に独創的で破壊的なイノベーションの創出に注力している。また、産業高度化に向けて、先端技術を生かした旧来産業の改造・レベルアップと新興産業・未来産業の育成に加え、サプライチェーンの強化とデジタル経済の推進に取り組んでいる。さらに、生産要素の質と配置の改善のために、生産要素の流動化を促す市場化改革と、教育・科学技術・人材の三位一体改革に加え、新しい生産要素としての「データ」の活用を進めている。
- 新質生産力の発展を反映して、中国は科学技術大国として浮上し、産業の高度化とグリーン転換も進展している。その一方で、米中デカップリングの影響や、挙国体制の限界、ベンチャー企業への資金提供の不足など、克服しなければならない課題も多い。これらの課題を解決するためには、市場化改革と対外開放の推進や、法治と私有財産の保護の強化などの制度改革を通じて、ビジネス環境の改善に努めなければならない。
関根 栄一
要約
- 中国では、2024年に入り、11年ぶりとなる中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議が開催され、「新たな質の生産力」の発展を促進するという新たなイノベーション政策が打ち出され、私募ファンド投資に関するエコシステムを形成していく方針も確認された。そのための資本市場の機能活用では、機関投資家の株式運用を促進するとともに、上海の科創板(新興市場)改革を進めていく方針を確認した。
- 「新たな質の生産力」にふさわしいイノベーションの促進に向け、投資家から見て魅力的な銘柄への投資機会が提供されるエコシステムの形成が重要になっており、国務院(内閣)及び科創板を有する上海市政府は創業(起業)投資を促す為のガイドラインを策定し、M&Aや新規株式公開(IPO)を通じた投資の出口(エグジット)ルートを整備する方針でもある。
- 創業投資を担う私募基金の管理残高を見ると、新型コロナウィルス(新型コロナ)の流行防止に伴う行動制限の影響を受け、2022年以降、管理残高の伸びが鈍化傾向にある。投資案件数ベース(累計)でエグジット率を試算すると、2022年は平均で32.4%となっている。
- 他に、科学技術部系研究院のアンケート調査では、新型コロナ流行期間、2022年の出口ルートは、IPOの23.86%、M&Aの11.03%に対し、株式買戻しが51.09%と過半となった。同調査では、ベンチャーキャピタル(VC)が期待する政策として、キャピタルゲインの二重課税防止に向けた税制優遇政策の整備や、政策性基金の設立が挙げられている。そのうち後者では、上海市政府はアーリー期の科学技術企業向け基金を新たに設立する計画である。
- 一方、同調査によると、2022年の創業投資の資金提供者では、国有・政府資金が全体の54.54%を占め、新興企業への公的資金による支援度合いが高まっている。民間VCによる投資をクラウディングアウトしないよう、外資を含めた多様な投資家層が参加するエコシステムの形成が求められている。併せて、投資・回収サイクルを確立するため、投資銀行の機能をうまく使ったエクイティストーリーの描き方も重要となっている。
橋口 達、坂上 聖奈
要約
- 近年、金融市場におけるデータの重要性が一層高まっている。規制当局に提出するデータの粒度や頻度は高まり、他社との差別化のためのデータへの投資の重要性も増している。データ事業を巡る買収は活発化しており、その中で格付会社が重要な役割を担っている。
- 信用格付市場は、金融危機以降、米国の証券規制における格付の参照が取り除かれるなどの環境変化があったが、現在もS&Pグローバル、ムーディーズ、フィッチの寡占が続いている。他方、S&Pグローバルとムーディーズは、データ事業を中心とする新たなビジネスモデルを構築することで、市況に左右される格付事業への依存度を下げてきた。
- S&Pグローバルは、不採算事業の売却やIHSマークイットとの合併を通じて、信用格付以外の事業に注力してきた。現在は、金融市場においてデータ販売に留まらない、金融市場の業務効率化を図るソリューションの提供者として、グローバル市場の活性化に寄与している。
- ムーディーズは、統合リスク評価を標榜し、現在では、信用リスクに留まらず、気候変動リスクやサードパーティ・リスクの理解、評価、管理、低減を支援する企業に変貌した。
- 金融危機以降の両社の株価は、大手金融機関を大きくアウトパフォームする。格付事業の高収益性や、格付以外の事業の安定性や成長性が市場から高く評価されている様子が窺える。両社の取組は、市況に影響を受けやすい金融グループにとっても、金融資本市場における自身の役割を再定義し、市場から評価される事業ポートフォリオを構築するにあたり、参考になるものと思われる。
野村 亜紀子
要約
- 確定拠出年金(DC)は2001年の導入以降、度重なる制度改革を行ってきた。直近では、2024年12月の「令和7年度税制改正の大綱」に、実現すれば10年ぶりとなる拠出限度額の引き上げが盛り込まれた。遡れば、2016年の改正DC法によるiDeCo(個人型DC)加入対象拡大や、指定運用方法の導入などが挙げられる。
- DCの加入者数は着実に増加し、2024年3月時点で1,100万人を超え、確定給付型年金(DB)を上回った。同時点の資産残高は29兆円だった。加入者による運用指図は、当初は預貯金及び保険商品が6割を占めたが、徐々に投資信託比率が上昇し、2024年3月時点で約7割に達している。
- もっとも、現役世代に占めるDC加入者の割合は2割に満たない。個人金融資産に占めるDC資産の割合も僅か1.3%で、投信比率の上昇基調も定着するのか注視する必要がある。日本は2040年代に65歳以上人口が最大になり、それ以降も人口に占める割合は上昇し続ける。超高齢社会に突入するまでの今後20年間、自助努力の資産形成を最大限支援する体制整備が極めて重要であり、DC制度改革はその鍵を握る。
- 最終的には、DC制度の拡充を通じて、老後生活を不安なく過ごせる高齢者を、可能な限り大勢生み出すことが目標となる。将来不安の払拭が消費拡大に繋がれば、税収増や経済成長にも寄与し得る。私的年金が、個人のファイナンシャル・ウェルネス向上、そして社会・経済の安定に貢献する存在になることを目指したい。
宋 良也
要約
- 中国では2022年11月25日、個人型の確定拠出型年金制度として、「口座型」個人年金制度の試験運用が開始された。2023年末時点で、加入者数は既に5,000万人超となっている。少子高齢化が進展する中、持続可能な運営に支障を来す恐れがある公的年金(基本養老保険)と、カバー率の更なる拡大が難しい職域年金を補完する役割が期待されている。
- 「口座型」個人年金制度の試験運用が続く中、加入者の拡大は鈍化しつつある。その要因として、税制優遇措置を享受できる潜在的な加入者が限られることなどが挙げられる。また、加入者が拠出する掛金額の低下、十分な長期・分散投資が図られていないなどの課題が生じている。その要因としては、年金ターゲットファンドによる長期投資が出来ていないことや、加入者の金融リテラシー不足が挙げられる。
- これらの課題を解決するためには、日米欧などの先進国における個人年金制度の拡充策が参考となろう。例えば、個人年金への加入拡大を図るには、自動加入制度の導入や、TEE型の税制優遇措置の導入が考えられる。また、個人年金の運用改善のための施策としては、長期分散投資を促す商品設計や、運用指図を行わない加入者向けのデフォルト商品の設定、証券会社による投資アドバイス提供に関する制度の整備、といった施策が考えられる。
野村 亜紀子、中村 美江奈
要約
- 「資産運用立国実現プラン」の一環でアセットオーナー・プリンシプルが2024年8月に策定され、今後の焦点は、5つの原則がいかに有効活用されるかである。海外事例からの示唆を得るべく、オーストラリアの年金基金最大手であるAustralianSuper(AS)の資産運用と各原則の対比を試みた。
- ASは加入者数340万人、資産残高3,500億豪ドル超の大規模アセットオーナーである。グローバル投資とインハウス運用の拡大を並行して進めており、非上場資産への投資、アクティブ運用にも積極的である。オーストラリア経済への貢献も意識している。また、財務的リターン追求を前提に、自国のエネルギー・トランジションへのコミットメントを明示している。これらの取り組みは、日本の大規模アセットオーナーにとって参考になるものと思われる。
- ASは確定拠出型年金(DC)であり加入者が運用指図するが、9割がデフォルト・ファンドであるバランス型ファンドに投資している。デフォルト・ファンドを含む主要な運用商品の運用目標は、「消費者物価指数を○%超上回る」である。インフレーションに勝つことは、年金基金に限らず、長期運用を手掛ける日本の学校法人や財団法人などにとっても、運用目標上、外せない論点であろう。
- ASの資産運用に対する積極的な取り組み姿勢は、アセットオーナーが目的・目標の最低限を満たすのに留まらず、更なる努力をすることをどう考えるかという論点に繋がる。これは、全てのアセットオーナーが、フィデューシャリーとして真摯に検討し判断するべきことと言えよう。
齋藤 通雄
要約
- 第二次世界大戦後の日本は、非募債主義を原則とする財政法の下、国債発行を行わずに財政運営をスタートしたが、1965年度に転機を迎えた。それから約60年に及ぶ国債発行の歴史を振り返ると、大きく4つの期間に分けて整理することができるように思われる。
- 第Ⅰ期は、国債発行が始まった1965年度から1974年度までで、財政法第4条に基づく建設国債の発行が中心だった期間である。この間に、国債の発行方式として、募集取扱及び引受を行うシンジケート団による、シ団引受が確立するとともに、償還方式として、今日まで続く60年償還ルールが整備された。
- 第Ⅱ期は、1975年度から1997年度までである。この期間においては、特例法に基づく赤字国債の発行を余儀なくされ(途中バブル期には赤字国債から一時脱却したが)、国債発行額が増大するとともに、その円滑な消化を図るため、新たな発行方式として公募入札等が導入され、年限の多様化も進展した。また、引受金融機関に要請されていた国債の売却自粛要請が緩和されるなど、流通市場の発展も進んだ。
- 第Ⅲ期は、1998年度から2012年度までで、国債管理政策が市場機能重視に大きく舵を切った期間である。発行方式として、主要先進国と同様のプライマリー・ディーラー制度が導入され、シ団引受は廃止された。また、即時銘柄統合方式の導入や流動性供給入札の導入など、流通市場での流動性を意識した発行が進んだ。さらには、5年債、30年債等の導入により、発行の軸となる年限構成が主要国と同様となり、非居住者向け非課税制度も整備されるなど、発行・流通全般にわたりグローバル・スタンダードに即した制度が整えられた。
- 第Ⅳ期は2013年度以降で、金融政策の転換により、国債市場における日本銀行の存在感が極めて大きくなるとともに、流動性が低下したり、イールドカーブが歪んだりといった事象も発生した。
- 2024年後半は、金融政策の再転換に伴い、第Ⅳ期がまさに出口を迎えている。日本銀行に替わる国債の買い手となるのは誰か、流動性の回復や金利形成がどのように進むのか、市場の安定を維持できるかなど、引き続き注視していく必要がある。
江夏 あかね
要約
- 21世紀の地方債市場は、市場公募化が進展する中で、金融政策を始めとして金融市場全般の動きの影響も受けたが、地方債の安全性を守る仕組み、地方債関連制度の進化、各地方公共団体による地方債の安定消化を意識した取り組み等を背景に、総じて安定して推移した。
- 地方財政は、財政の硬直化傾向はあるものの、地方公共団体の財政健全化努力や国からの財政移転にも下支えされ、改善傾向が確認された。ただし、今後の地方財政の持続可能性を考えると、厳しい国の財政状況、地方公共団体の厳しい財政運営の舵取り等の課題を抱えていることが明らかになった。
- 今後も、地方公共団体にとって地方債が重要な財源の1つである状況は不変と想定され、地方債市場から安定的に資金調達が行えるとともに、同市場の持続可能性が維持されることが大切なのは言うまでもない。そのための主な論点としては、(1)資金調達コスト低減に向けた取り組み、(2)臨時財政対策債のさらなる縮減、(3)減債基金の効率的な運用、が挙げられる。
- 特に、2001年度に創設された臨時財政対策債は、2025年度地方債計画において、2025年度の発行額が制度が始まって以来初となるゼロとされた。地方財政の健全性の観点から評価されるものの、発行残高(2025年度末見込み、約42兆円)を踏まえると、フローの発行額とともに、ストックの発行残高についてもさらに縮減していくことが求められる。
富永 健司
要約
- 国内の社債市場において、調達資金が持続可能な開発目標(SDGs)に貢献する事業に充当されるSDGs債は、発行の裾野が着実に広がっており、2023年度の発行額は約2.8兆円、社債の発行額全体に占めるSDGs債の割合は2割超に達した。
- 日本の社債市場におけるSDGs債は、2010年代後半に環境省の発行支援策の後押し等も背景に、グリーンボンドを中心に発行規模が拡大した。2020年代に入って、日本政府による重層的な支援を受けながら、トランジションボンドの発行実績が増えつつある。
- 社債市場においてSDGs債の発行拡大が進む中、(1)社債発行に占めるSDGs債の割合の上昇、(2)業種及び発行体の多様化、が進展している。中長期的な観点から、SDGs債による資金調達ニーズ、SDGs債の対象プロジェクトの広がり、一般社債対比の発行条件等を踏まえた、企業によるSDGs債の発行に向けたさらなる取り組みが注目される。
- 今後のSDGs債を含む社債市場を見据えると、国内外の金融政策、主要各国における選挙、地政学リスク等により、先行きを見通すのが困難な状況にあると言える。このような状況も踏まえた上で、SDGs債の市場発展に資する論点としては、(1)投資家層の拡大に向けた取り組み、(2)インパクトレポーティングの比較可能性の向上、が挙げられる。発行体がこれらの取り組みを進めることを通じて、日本のSDGs債市場全体がさらに活性化することが期待される。
北野 陽平
要約
- 世界第5位の経済圏であるASEANでは、長期的に持続可能な発展に向けた取り組みを推進していく上で、サステナブルファイナンスの重要性が高まっている。近年、持続可能な開発目標(SDGs)に資するSDGs債の発行が拡大するとともに、温室効果ガス排出量実質ゼロ(ネットゼロ)目標の達成に向けてトランジション・ファイナンスが促進されている。
- ASEANのSDGs債市場では、グリーンボンドとサステナビリティボンドが成長をけん引しているが、近年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)への関心が高まりつつある中、2024年11月にタイ政府によりアジアの政府として初となるSLBが発行された。また、国際開発金融機関等の支援を得てSDGs債を発行する域内企業が増加している。
- 2023年10月に発行された「ASEANトランジション・ファイナンス・ガイダンス(ATFG)」の初版では、信頼できるトランジションの要素が明確化されるとともに、トランジションを進める事業体を分類する枠組みが導入された。2024年10月に発行されたATFG第2版では、トランジション・ファイナンスの定義・範囲がより明確化され、トランジション・パスウェイ(移行経路)を適切に選定するためのプロセスが示されている。
- シンガポールは、ASEANにおけるトランジション・ファイナンス促進で主導的な役割を担っており、官民連携の取り組みとしてブレンデッド・ファイナンスを強化している。また、シンガポール金融管理局(MAS)は、石炭火力発電所の早期閉鎖を加速させるために信頼性の高いカーボンクレジットを利用すべく、トランジション・クレジット連合を立ち上げ、同連合の下でフィリピンにおける試験的なプロジェクトを推進している。
- 今後、ASEANがトランジション・ファイナンスをさらに促進していく上で日本との協力強化の可能性が注目される。特に、①トランジション・ボンド発行に係るノウハウの提供、②ASEAN域内の政府等により発行されるトランジション・ボンドへの投資、③トランジションに資するカーボンクレジット創出プロジェクトの開発支援、の3点が期待される。
関田 智也
要約
- トランジション・ファイナンスへの注目が近年さらに高まっているものの、当該市場には発展の余地がある。債券市場を見ると、グリーンボンドの発行額が大きく伸長している一方、トランジション・ボンドの市場規模は現時点でわずかなものに留まっている。特に、グリーンボンドの活用につき、他の地域と比較して大きく進んでいる欧州が、トランジション・ボンドの発行や投資で後れを取っている点は、注目に値する。
- 欧州連合(EU)は最近、トランジション・ファイナンスの活用を促す情報発信を積極化し始めている。こうした情報発信の背景には、トランジション・ファイナンスの活用を通じて、サステナブルな金融商品の供給を増やしたいというEUの意図が働いている可能性がある。
- 国際資本市場協会(ICMA)は、トランジション・ファイナンス市場の拡大を促進し得る政策の方向性として、①政府及び市場によるガイダンスの整備、②企業による標準化された移行計画の開示促進、の2種類を挙げている。これに関連して、EUでは、欧州委員会による「トランジション・ファイナンス勧告」を通じて、企業がトランジション・ファイナンスを活用するためのガイダンスが提供されている。英国では、トランジション・プラン・タスクフォース(TPT)が公表した移行計画の開示フレームワークを契機に、企業による標準化された移行計画の開示促進が図られている。
- EU及び英国の取り組みを契機に、欧州におけるトランジション・ファイナンスの活用推進が見られれば、当該市場の成長はさらに加速する可能性がある。一方で、トランジション・ファイナンス市場及びそれを取り巻く制度は、日本を中心として、相応に整備が進んでいるという現状がある。これから市場拡大を図っていく段階にある欧州においては、トランジション・ファイナンスを巡る諸制度・規制につき、先行地域との整合性を意識することも求められよう。
板津 直孝
要約
- サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は2024年3月、日本におけるサステナビリティ開示基準の公開草案を公表した。同公開草案は、プライム上場企業における有価証券報告書での開示を想定する。同公開草案に基づく非財務情報は、国際財務報告基準(IFRS)のほかに、日本会計基準や米国会計基準及び修正IFRSに基づいて作成された財務諸表に対しても、補完することができるとしている。公開草案の最終化後、金融庁が法定開示への適用を検討する予定であるが、日本の基準の位置付けが明確になったことを踏まえ、投資家及びグローバル企業は、先行する欧米の開示要請との違いを整理することが重要となる。
- 公開草案の基準構成や開示要件は、概ねIFRSサステナビリティ開示基準と同様であるが、日本の法令等を踏まえた公開草案独自の規定を定めている。独自に追加した開示は、IFRS サステナビリティ開示基準に基づく開示情報作成の過程で入手する情報の範囲内で、作成可能なものに限定されている。
- 公開草案は、情報利用者として投資家を想定し、財務上の重要性を概念としている。連結子会社などからの温室効果ガス(GHG)排出量の開示では、財務会計で用いられている連結基準と同じ基準を適用することが、GHGプロトコルが推奨する排出量報告の目的適合性を満たすことになる。現行のIFRSなどの連結基準を踏まえると、経済的実質を優先して適用する持分割合アプローチが相当すると言える。
- ただし、公開草案ではアプローチの選択適用を認めている。そのため、選択したアプローチが連結財務諸表に含まれる事業体の範囲と異なる場合は、排出量の測定と財務会計との結合性、さらには連結財務諸表との整合性と比較可能性も損なわれる懸念に、留意する必要がある。
小立 敬
要約
- 近年、世界的に金融デジタル化が進展している。金融デジタル化は、金融機関や消費者に便益をもたらす一方、新たな脆弱性を生み出し、金融機関やその顧客、市場参加者、さらには金融の安定へのリスクを増幅させる可能性も想定される。そのため、金融デジタル化が金融機関や金融システムにもたらすリスクに関する議論も始まりつつある。
- 金融安定理事会(FSB)は2024年11月、人工知能(AI)が金融安定に与える影響に関するインプリケーションを議論する報告書を策定し、金融セクターにおけるAI導入をレビューした上で、AIが金融の安定に与える脆弱性として、①サードパーティへの依存とサービスプロバイダーの集中、②市場相関性、③サイバー、④モデルリスク、データの品質およびガバナンスという論点を指摘した。
- バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は2024年5月に公表した報告書において、金融デジタル化に関するリスクとして、①戦略リスク、②レピュテーショナルリスク、③オペレーショナルリスク、④データ関連リスクを挙げた上で、新たなテクノロジーが金融の安定に与える脆弱性として、①相互連関性の増加、②規制アービトラージ、③感染、④金融リスクの増幅、⑤フラグメンテーションリスク、⑥集中リスクを指摘する。
- AI導入を含む金融デジタル化が金融の安定にもたらすリスクについて世界的に関心が高まりつつある中、国際基準設定者や各国・地域の金融当局が検討を進めた結果、どのような政策措置が講じられたり、金融機関にどのようなリスク管理やガバナンスの構築が要求されたりするのかについて、今後注目する必要があるだろう。
江夏 あかね
要約
- 人工知能(AI)が急速に発展・普及する中で、リスクを管理・抑制しつつ最大限の便益を得ることを目的とするAIガバナンスの重要性が世界的に認識されてきた。
- 各国・地域でスタンスは異なるものの、政府は法規制・ガイドライン等の対応を進め、企業自身も取締役会の監督体制や指針の整備、情報開示等の対応を進めている。さらに、近年は投資家も投資先企業のAI関連リスクに着目し、原則・ガイドラインの策定や情報開示等の対応を求めているほか、幅広いセクターの企業における対応状況に着目しつつある。
- 金融資本市場の観点から、AIガバナンスを企業等にさらに浸透させていくことは、企業価値維持・向上、ひいてはリスク調整後の投資パフォーマンスの維持・向上にもつながり得るため、重要と言える。
- その意味での今後の論点としては、(1)AIガバナンスの重要性に関する理解の促進、(2)情報・データの適切な開示、(3)第三者評価等の仕組みの整備、が挙げられる。特に、1点目について、米運用大手のフェデレーテッド・ハーミーズのように企業に対してAIに関するエンゲージメントを行う投資家が近年見られるようになっている。投資家が企業に対してエンゲージメントを実施するに当たっては、AIは、情報技術(IT)面のみの課題ではなく、企業価値に影響を及ぼし得る重要な経営課題であることを繰り返し伝え、企業の経営陣における意識向上を促すことが大切と言える。